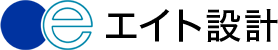こんにちは、エイト設計建築部です😊
今回は小樽を散策したときに見かけた屋根の甍(いらか)についてお話をしようと思います。
以前、井上靖作「天平のいらか」を読んで甍について調べたことがあります。甍とは瓦屋根の頂上に葺いた棟瓦を云うようですが、あまり聞き覚えが無いかもしれません。
実は子供のころに歌った鯉のぼりの歌詞で「いらかの波と雲の波、重なる波のなか空を橘(たちばな)かおる朝風に、高く泳ぐや鯉のぼり」とありますが、「いらか」の意味も分からず歌っていました🤭
また、「甍を争う」という慣用句があります。家々がすき間なく立ち並んでいるという意味で、当時の豪商たちが富の力を誇示するため屋根の高さを競うように建てたことから来ているようです。


※他にも「うだつが上がらない」という慣用句の語源となったうだつがありました。写真に写るのは袖うだつと呼ばれるもので、防火壁と装飾を兼ねています。(2枚目)
同様に、中世イタリア(14世紀頃)のサンジミニャーノでは町の人たちが富の力を誇示するために、必要もない塔を競って建てていたそうです(最盛期には72本も!)。
現在も14本残っていますが、実際必要な塔は3本だけだったようで他の町からは、「靴や洋服に見栄を張るのは何ともないが、見栄を張って塔を建てたサンジミニャーノ」と揶揄されていたようです。
しかし今では世界遺産となり、有名な観光都市になっているので分からないものです!

(35年ほど前に実際に見てきた塔の写真です📸下はパンフレット掲載のもの)

塔の中は階段のみで、屋上からはトスカーナの緑豊かな田園風景を観ることができます。
甍も塔も人々の見栄から始まったことですが、こう見るとたまには見栄を張って生きるのも良いのではないかという気がします。